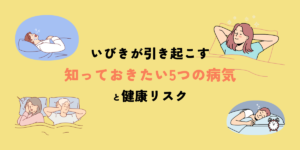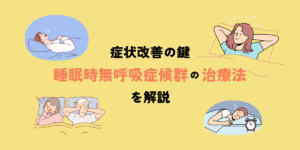睡眠時無呼吸症候群の重要性
「最近、いびきが止まったかと思うと、無呼吸になっているのでは…と不安になることはありませんか?」
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に呼吸が一時的に止まる、または著しく弱まる状態を指します。単なるいびきとは違い、放置すると心臓病や脳卒中のリスクが高まり、日常生活にも影響を及ぼす可能性があります。
例えば、日中の強い眠気や集中力の低下、慢性的な疲労感。これらが家族全体の生活に影響していませんか?
この記事では、SASの原因や3つのタイプをわかりやすく解説し、治療に向けた最初のステップをお手伝いします。「どう対処すればいいの?」という疑問に答え、家族みんなが安心して眠れる日常を取り戻すお手伝いができれば幸いです。
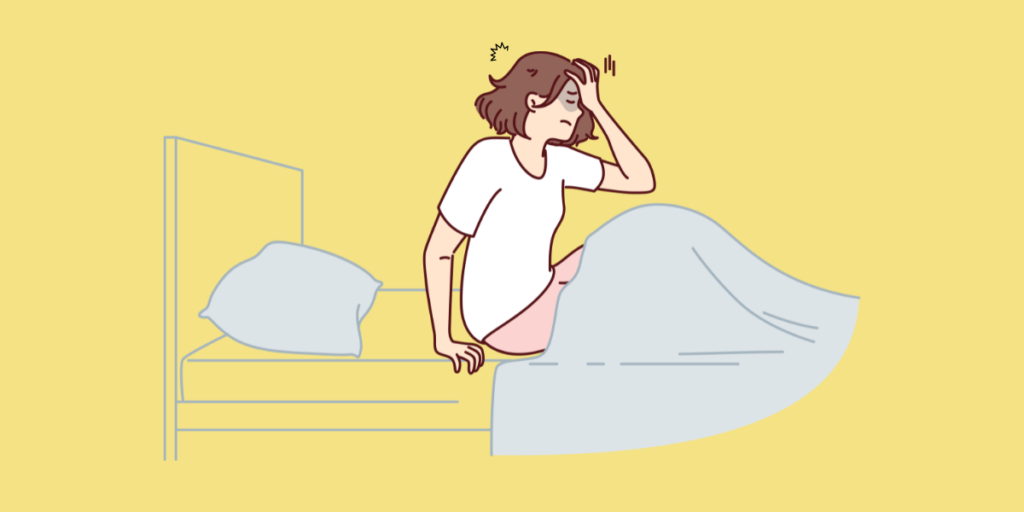
睡眠時無呼吸症候群とは?
「いびきが止まったかと思うと、しばらく呼吸がないように見える…」これが頻繁に起きている場合、それは 睡眠時無呼吸症候群(SAS) かもしれません。
睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠中に呼吸が10秒以上止まる状態が繰り返し発生する疾患です。具体的には、1時間に5回以上の無呼吸が認められる場合や、無呼吸が一晩(7時間の睡眠中)に30回以上認められる場合は、この疾患に該当する可能性があります。
日本では、成人男性の約4%、女性の約2%がこの疾患を抱えているとされ、決して珍しいものではありません。特に、以下の要因がリスクを高めると言われています。
- 肥満:首回りに脂肪がつき、気道が狭くなる
- 加齢:喉の筋肉が弱くなりやすい
- 生活習慣:アルコールや喫煙、睡眠不足などが影響
こうした要因が重なると、旦那さんの健康だけでなく、家族全員の生活の質にも影響を与える可能性があります。睡眠時無呼吸症候群について正しい知識を持ち、早めに対処することが大切です。
3つのタイプを徹底解説
いびきを気にして調べていると、「睡眠時無呼吸症候群には種類がある」と聞いたことがあるかもしれません。この疾患には、原因や治療法が異なる3つのタイプがあります。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)
最も多く見られるタイプで、気道が狭くなることによって呼吸が妨げられる状態です。
- 原因
-
肥満によって首回りに脂肪が蓄積されると、気道が圧迫されることがあります。また、口蓋垂(のどちんこ)や軟口蓋の形状に異常がある場合も、気道が狭くなりやすくなります。さらに、扁桃腺が大きいと、それが呼吸の妨げとなることもあります。
- 主な症状
-
このタイプの無呼吸症候群では、夜間に激しいいびきをかくことが特徴です。また、息苦しさのために途中で目が覚めることがあり、結果として睡眠が浅くなります。日中には強い眠気を感じたり、集中力が低下したりすることがよくあります。
- 治療方法
-
- CPAP(シーパップ):睡眠中に空気を送り込み、気道を広げる装置を使用します。
- マウスピース:歯科医が作成するもので、顎の位置を調整して気道を確保します。
- 外科手術:必要に応じて、軟口蓋や口蓋垂を調整して気道を広げる手術が行われます。
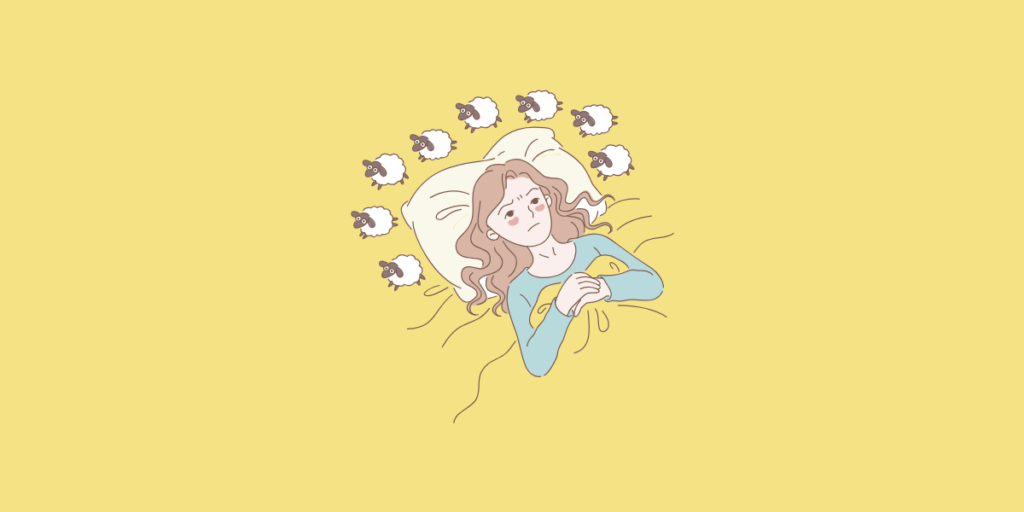
中枢型睡眠時無呼吸症候群(CSAS)
こちらは少し珍しいタイプで、脳から呼吸の指令が出なくなることが原因です。
- 原因
-
このタイプは、心不全や脳卒中などの疾患が原因となることが多いです。これらの疾患によって、脳の呼吸中枢が正常に働かなくなる場合があります。また、麻薬性鎮痛薬など一部の薬が副作用として中枢型の無呼吸を引き起こすこともあります。
- 主な症状
-
中枢型では、無呼吸中に呼吸をしようとする動き自体が見られないことが特徴です。また、いびきがあまりないため、気づきにくい場合もあります。ただし、日中の眠気や疲労感は、他のタイプと同様に現れることがあります。
- 治療方法
-
- 薬剤の調整:原因となる薬の見直しや、新しい薬の処方が行われます。
- CPAP:CPAPは基本的にOSASに適応される治療法ですが、CSASにも一定の効果が見込め、薬物療法と合わせて行われることが多いです。

混合型睡眠時無呼吸症候群
その名の通り、OSASとCSASの両方の特徴を持つタイプです。
- 原因
-
混合型睡眠時無呼吸症候群は、閉塞型と中枢型の両方の要因が絡み合って発生します。たとえば、気道の狭さが原因で閉塞型の症状が現れる一方で、脳が適切に呼吸を指令できず中枢型の症状が加わる、といった複合的なメカニズムが見られます。
- 治療方法
-
混合型睡眠時無呼吸症候群の治療は、まず閉塞性睡眠時無呼吸症候群の治療法と同様のアプローチから始めます。その後、中枢型の要因に対応する治療法が適応される場合もあります。閉塞性の症状が改善しても中枢型が残るケースでは、医師による継続的な経過観察と治療法の調整が重要です。
睡眠時無呼吸症候群の原因
「どうして無呼吸になってしまうのだろう…?」そんな疑問を感じている方も多いかもしれません。睡眠時無呼吸症候群(SAS)の原因には、次のような具体的な要因が考えられます。
- 肥満
-
喉周りの脂肪が気道を圧迫するため、肥満はSASの主な原因とされています。特に首回りが太くなると、気道が狭まりやすくなります。
- 骨格の問題
-
小さな下顎や後退した顎の形状、扁桃腺の肥大などの骨格的要因も、気道を狭める原因となります。これらの特徴は生まれつきの場合もありますが、加齢により悪化することもあります。
- 加齢
-
年齢を重ねるにつれ、喉周りの筋肉が弱まり、気道が閉塞しやすくなるため、高齢者はSASのリスクが高まります。
- アルコールや睡眠薬の使用
-
筋肉の緩みを助長するアルコールや睡眠薬は、気道を閉塞させる可能性があります。夜間に摂取することは特に注意が必要です。
- 女性特有のリスク
-
更年期や妊娠中のホルモン変化がSASを引き起こす場合があります。特に更年期では、筋肉の緩みや代謝の変化により症状が現れやすくなります。

診断と治療の流れ
専門医の受診
まずは、睡眠外来や耳鼻咽喉科を受診しましょう。医師は問診や診察を通じて症状やリスク要因を確認し、必要に応じて検査を勧めます。日中の眠気やいびきの頻度を伝えると診断がスムーズです。
簡易型アプノモニター検査
最初のステップとして、自宅で行える簡易型の検査が用いられることがあります。この検査では、鼻や指先にセンサーを取り付けて睡眠中の呼吸状態を記録します。簡易検査の結果によって、次の精密検査が必要か判断されます。
ポリソムノグラフィー(PSG)検査
より正確な診断を行うために、専門施設でのポリソムノグラフィー検査が実施されることがあります。この検査では、睡眠中の脳波や呼吸、心拍数、血中酸素濃度などを詳細に記録します。これにより、SASのタイプや重症度が明らかになります。また、この検査は施設に宿泊(入院)しての検査になります。
治療開始
診断結果に基づき、症状に応じた治療法が提案されます。
- CPAP(持続的気道陽圧療法): 空気圧で気道を開き、呼吸を確保する装置を使用
- マウスピース: 顎の位置を調整して気道を広げる装置
- 外科手術: 気道の構造を改善する手術
適切な治療を受けることで、いびきや無呼吸が改善し、旦那さんだけでなく家族全員の生活の質も向上します。
早期診断が鍵
放置すると健康リスクが高まるSASですが、早期に診断して治療を開始すれば、多くのケースで症状を改善できます。心配がある場合は、ぜひ専門医へ相談し、適切なケアを始めましょう。

家族ができるサポート
睡眠中に無呼吸の症状を示していると気づいたら、家族はどのようにサポートできるかを考えてみましょう。いびきや無呼吸は本人が気づきにくい問題ですが、家族の支えが治療の第一歩になります。
睡眠中の様子を観察
まず、睡眠中の様子を観察することが大切です。
- 呼吸停止の回数: 無呼吸のエピソードがどのくらいの頻度で起こっているかを確認。
- いびきの変化: いびきが一貫しているか、それとも途中で止まるようなパターンがあるかを記録します。
観察結果は専門医の診察時に重要な情報となり、診断の助けになります。
治療をサポート
診断や治療が進んだ後も、家族としてのサポートが重要です。
- CPAPの使用を励ます: 持続的気道陽圧療法(CPAP)の装置は、最初は慣れるのが難しい場合があります。旦那さんが継続的に使えるように、ポジティブな声かけをしましょう。
- 生活習慣の改善を一緒に実行: 例えば、夕食後の散歩を習慣にする、アルコールの量を減らすなど、生活習慣の改善を二人で取り組むことで成功率が上がります。
専門医の受診を促す
「いびきくらい大丈夫」と軽視されがちな問題ですが、放置すれば健康リスクが高まります。ためらう場合は、優しく説得して早めの診察を促しましょう。あなたの真剣な気持ちが伝われば、行動を起こしやすくなるはずです。
家族の力で快適な睡眠を取り戻そう
いびきや無呼吸が「もしかして病気かも?」と気になり始めたら、それは大切なサインです。睡眠時無呼吸症候群は、適切な診断と治療、そして家族の協力があれば改善できる疾患です。
家族の健康と生活の質を守るために、まずは専門医に相談してみましょう。その一歩が、健康だけでなく、ご家族全員の快適な睡眠と安心した日常につながります。
また、生活習慣の見直しや治療のサポートを一緒に行うことで、より良い結果が期待できます。大切なのは、焦らず継続的に向き合っていくこと。
ぐっすり眠り、元気に過ごせる毎日を取り戻すために、家族みんなで力を合わせていきましょう。少しずつでも、前進することで必ず改善の道が見えてきます!